「ふるさと納税って、なんだかお得らしいけど、手続きが面倒くさそう…」
「税金とか控除とか、言葉が難しくてよくわからない…」
40代にもなると、お金の話は避けて通れませんよね。でも一度覚えてしまえば何てことはないものがほとんどです。むしろ、始めない方がもったいないことばかり。まだ始めていない方はぜひ、この記事を読んで実践してみてください。
 さくら
さくらこの記事はこんな方におすすめです。
・ふるさと納税をまだしたことがない方
・ふるさと納税の仕組みがわからない方
・ふるさと納税を今年はやってみようと思っている方
この記事では、ふるさと納税の仕組みから具体的な手続き、そして私が感じていたメリットを紹介します。一緒に賢いお金との付き合い方を始めましょう!
「ふるさと納税って何?」今さら聞けない基本のキ
まず、ふるさと納税の仕組みをシンプルにお伝えしますね。ふるさと納税は応援したい自治体(都道府県や市区町村)に寄附ができる制度です。
「え、ただの寄附?」と思ったあなた、ここからがポイントです。
寄附をすると、その自治体からお礼として特産品などの「返礼品」がもらえます。さらに、寄附した金額のうち、自己負担額の2,000円を除いた全額が、翌年にあなたが支払う税金(所得税・住民税)から差し引かれる(控除される)仕組みです。
| ふるさと納税の仕組み(3ステップ) | 具体的な内容 |
| ① 好きな自治体に寄附する | 全国の好きな自治体を選んで、応援の気持ちを込めて寄附をします。 |
| ② 返礼品が自宅に届く | 自治体からお肉やお米、日用品といったお礼の品が届きます。 |
| ③ 翌年の税金が安くなる | 寄附した金額から2,000円を引いた額が、翌年支払う所得税や住民税から控除されます。 |
つまり、実質2,000円の負担で、さまざまな返礼品を受け取りながら、未来に払う税金を前払いしているようなイメージです。どうせ同じ額の税金を納めるなら、素敵なプレゼントがもらえる方が断然お得だと思いませんか?
40代独身の私がふるさと納税を始めた3つの理由
私がふるさと納税を始めたのには、3つの理由があります。
理由1:実質2,000円で生活が豊かになる「返礼品」の魅力
何と言っても一番の魅力はこれです!どうせ払う税金、少しでもモノに変えたいと思った私は毎年、お米やトイレットペーパー、冷凍のお肉などを返礼品でいただいています。
同じ税金を払うなら少しでも得な気分を味わいたい、そう思ったのがきっかけですが、誰よりも返礼品を楽しみにしているかもしれません(笑)
理由2:「税金の使い道」を自分で選べる社会貢献
通常、毎月お給料から天引きされる住民税。何に使われているかは、正直考えたことがありませんでした。
でも、ふるさと納税なら、寄附金の使い道を自分で選べるんです。「子育て支援に力を入れている町」「美しい自然を守りたい村」「災害からの復興を目指す地域」など、自分の意思で税金の使い道を指定できます。
ただ税金を納めるだけでなく、自分の想いを乗せて社会を応援できる感覚は、40代になった今だからこそ、より大きな意味を持つように感じています。自分の寄附金が、誰かのためになっていると実感できるのは、本当に嬉しいものですよ。
理由3:将来のためのお金の勉強になったから
ふるさと納税を始めるには、どうしても「控除」「所得税」「住民税」といった言葉と向き合う必要があります。最初は「難しそう…」と敬遠していましたが、自分のこととなると不思議と頭に入ってくるものです。
「私の年収だと、いくらまで寄附できるんだろう?」と調べるうちに、自然と税金の仕組みが理解できるようになりました。これは、iDeCoやNISAなど、将来のための資産形成を考える上でも、絶対に役立つ知識です。ふるさと納税は、マネーリテラシーを高める最高のきっかけになりました。


私はいくらまで寄附できる?控除上限額の調べ方
ふるさと納税で絶対に損をしないために、一番大切なのが「控除上限額」を知ることです。これは、「この金額までなら、自己負担2,000円で済みますよ」という寄附の上限のこと。この額を超えて寄附してしまうと、超えた分は純粋な自己負担になってしまうので注意が必要です。
まずは簡単シミュレーション!源泉徴収票を用意しよう
控除上限額の計算なんて難しそう…と心配しなくても大丈夫!ふるさと納税サイトには、誰でも簡単に上限額を計算できる「控除上限額シミュレーター」が用意されています。
より正確な金額を知るために、手元に源泉徴収票を用意しましょう。毎年年末か年明けに会社からもらう、あの書類です。シミュレーターの案内に沿って、源泉徴収票に書かれている「支払金額(年収)」や「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」などを入力するだけで、あなたの控除上限額の目安がすぐにわかります。
年収400万円〜600万円(独身)の控除上限額目安
「とりあえず、ざっくりとした目安が知りたい!」という方のために、総務省のデータなどを参考に、独身(または共働きで扶養家族がいない)の場合の年収別の控除上限額をまとめてみました。
| 年収 | 控除上限額の目安 |
| 400万円 | 約42,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 |
※上記はあくまで目安です。住宅ローン控除やiDeCo、医療費控除などを利用している場合は上限額が変わるため、必ずご自身でシミュレーターを使って確認してくださいね。
初心者でも簡単!ふるさと納税の始め方4ステップ
控除上限額がわかったら、いよいよ実践です!ネットショッピングと同じくらい簡単な4ステップで完了します。
ステップ1:ふるさと納税サイトを選ぶ
まずは、どのサイトで寄附をするか決めましょう。有名なのは「楽天ふるさと納税」「さとふる」「ふるなび」など。サイトによって、ポイント還元率や扱っている返礼品が違うので、自分に合ったサイトを選ぶのがおすすめです。(おすすめサイトは後ほど詳しく紹介します!)
ステップ2:応援したい自治体と返礼品を選ぶ
サイトが決まったら、いよいよ返礼品選びです。お肉、お米、フルーツ、日用品…本当にたくさんの種類があって、見ているだけでもワクワクします。応援したい地域や、寄附金の使い道から選ぶのも素敵ですね。
ステップ3:寄附を申し込む(クレカ決済が便利!)
欲しい返礼品が決まったら、ネットショッピングと同じ要領で申し込みます。名前や住所などを入力し、支払い方法を選択。クレジットカード(クレカ)決済なら、ポイントも貯まるし手続きもスムーズなので特におすすめです。
2025年10月にふるさと納税ポータルサイト独自のポイント付与は廃止されますが、クレジットカード決済によるポイントは引き続き付与されるので、クレカ決済がお得です。
ポイント廃止の記事はこちらを参考にしてください。
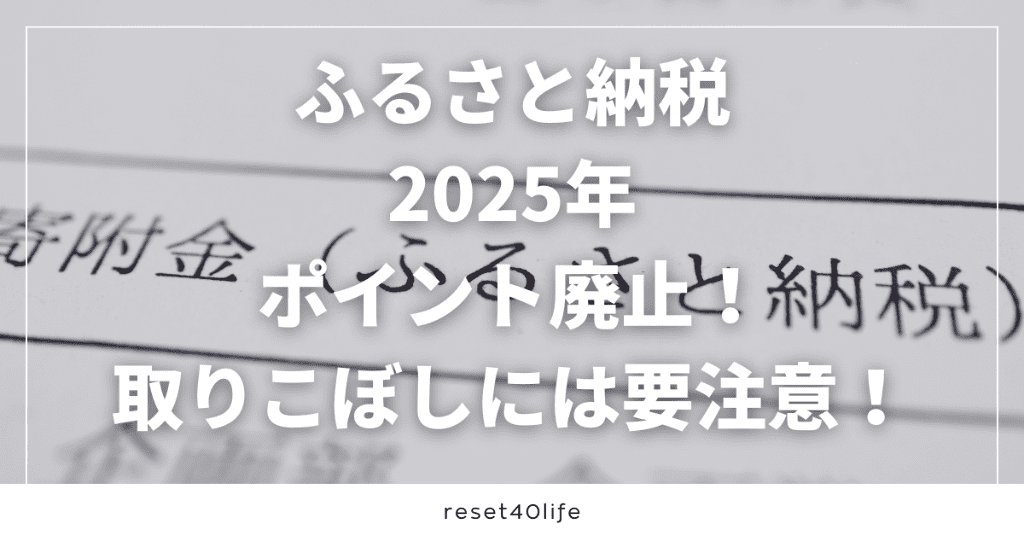
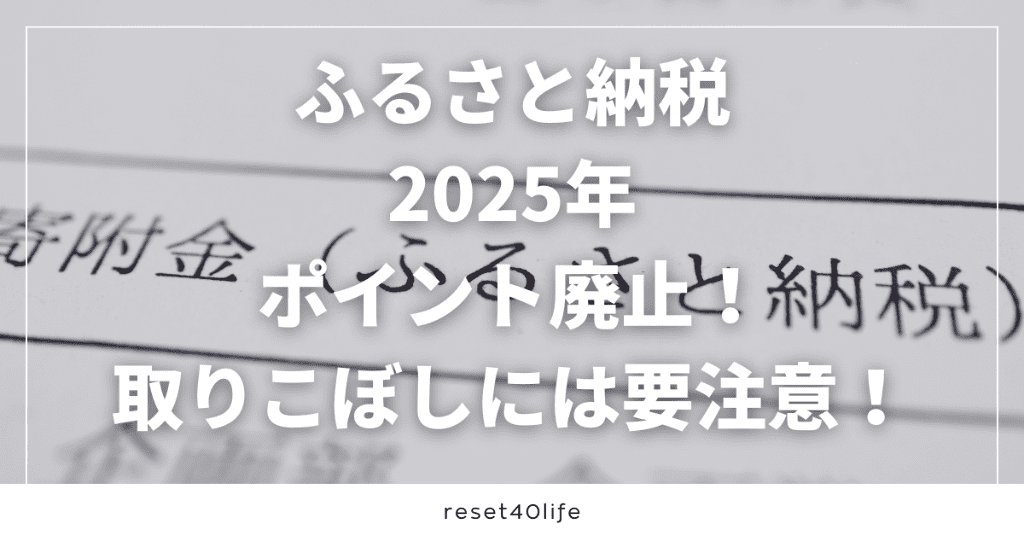
ステップ4:書類を受け取り、申請手続きをする
寄附が完了すると、後日、自治体から「寄附金受領証明書」という大切な書類と、「ワンストップ特例制度の申請書」が届きます。この書類を使って、税金の控除を受けるための申請を行います。
【重要】確定申告は必要?「ワンストップ特例制度」を使いこなそう
税金の控除って、確定申告が必要だと思う方がいるかもしれませんが、そう思っている方にこそ知ってほしいのが「ワンストップ特例制度」です。これは、特定の条件を満たせば、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる、とっても便利な制度です。
ワンストップ特例制度の対象になる人・ならない人
あなたがこの特例制度を使える対象かどうか、下の表でチェックしてみましょう。
| 項目 | 対象になる人(両方を満たす必要あり) | 対象にならない人 |
| 確定申告の要否 | もともと確定申告が不要な会社員など | 自営業者、医療費控除などで確定申告をする人 |
| 寄附先の自治体数 | 1年間の寄附先が5自治体以内 | 1年間の寄附先が6自治体以上 |
会社員で、他に確定申告をする予定がない方なら、ほとんどの場合で利用できます。
ワンストップ特例制度の申請方法と注意点
申請方法はとても簡単です。
- 自治体から届く「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入・捺印する。
- マイナンバーカードのコピーなどの本人確認書類を同封する。
- 寄附した翌年の1月10日(必着)までに、寄附した自治体へ郵送する。
最近では、スマホアプリで完結するオンライン申請も主流になってきました。郵送の手間や切手代もかからず、申請状況も確認できるので、私は断然オンライン申請をおすすめします!
オンラインの場合は専用のアプリで自治体から届いたQRコードを読み込んで手続きを行うものが多いです。やり方も簡単です。
ワンストップ申請や寄附管理を確認できるサービス「ふるまど」の場合、
- 申込時にオンラインを選択し、ふるさと納税を申し込む。
- 公的個人認証アプリ「IAM(アイアム)」のダウンロードする。
- メールが届き、「ふるまど」から寄付を登録。寄付(整理)番号が必要。
- 公的個人認証アプリ「IAM(アイアム)」を立ち上げ、マイナンバーカードを読み込む
上記のような流れで手続きできます。
「自治体マイページ」の場合、
- 自治体から送られてくるメールの▼自治体マイページ▼をクリック
- 自治体マイページに新規登録もしくはログイン
- 申請自治体を選択
- マイナンバーカードをかざし、暗証番号(4桁)を入れる
- 住所・氏名・電話番号などを確認
- 2つのチェック(①確定申告しない方②寄付先が5自治体以下)を入れる
- 申請内容を確認し、2回目のマイナンバーカード読み取りをする。※暗証番号は署名用電子証明書の番号
年末が近づくと申し込みが集中するため、早めに行動するのがポイントです。


医療費控除を利用する人は確定申告が必要。申告漏れに注意!
ここで一つ、とても重要な注意点があります。確定申告の必要がないサラリーマンでも、年間の医療費がたくさんかかって「医療費控除」を受けたい人は、確定申告が必要になります。
その場合は、ワンストップ特例制度は利用できません。確定申告をする際に、ふるさと納税の分も合わせて申告するのを忘れないようにしましょう。もし間違えてワンストップ特例の申請をしてしまっても、確定申告の内容が優先されるので安心してください。還付を受けるためにも、申告漏れには気をつけましょう。
【体験談】40代独身女性におすすめの返礼品ジャンル
「返礼品が多すぎて選べない!」という方のために、40代独身の私が実際に頼んで「これは当たり!」と思ったおすすめジャンルをご紹介します。
冷凍庫の味方!お肉やお魚のストック品
一人暮らしだと、大容量パックのお肉はなかなか買いづらいですよね。でも、ふるさと納税なら、小分けで冷凍されたハンバーグや豚肉スライス、鮭の切り身などがたくさん手に入ります。仕事で疲れて帰ってきた日も、冷凍庫にストックがあればサッと一品作れて本当に便利。食費の節約にも直結します。
毎日の食卓に。お米や野菜・フルーツ
お米やトイレットペーパーのような「必ず消費するもの」は、ふるさと納税の鉄板です。重たいお米を家まで運んでもらえるのは、地味に嬉しいポイント。また、旬のフルーツ(シャインマスカットやいちごなど)は、スーパーでは少し躊躇してしまう価格ですが、返礼品なら心置きなく楽しめます。
自分へのご褒美に!ちょっとリッチなスイーツやお酒
毎日頑張っている自分へのご褒美も大切。有名パティスリーの冷凍ケーキや、高級アイスクリームの詰め合わせ、普段は買わないようなクラフトビールや日本酒など、心ときめく返礼品もたくさんあります。これぞ、ふるさと納税の醍醐味です!
まとめ:ふるさと納税は、未来の自分への賢い投資
ふるさと納税は、単なる節税やお得な制度ではありません。
- 好きなものが選べる「返礼品」
- 社会に貢献できる「税金の使い道」
- 将来に役立つ「お金の知識」
これらすべてを、たった2,000円の負担で手に入れられる、未来の自分への賢い投資だと私は思っています。税金の制度は時々見直されることもあります。だからこそ、後回しにせず、思い立った今、始めてみるのが一番です。
