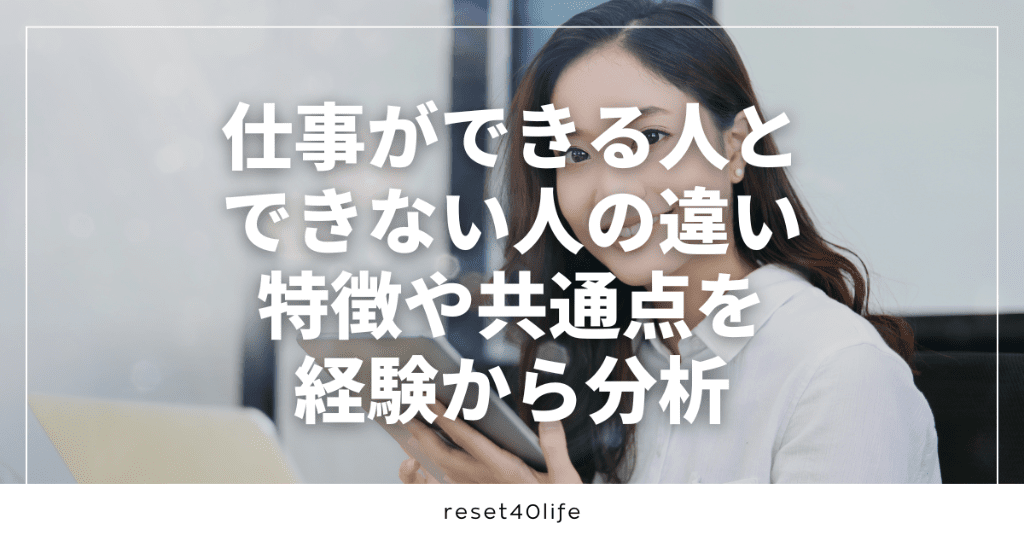周りの同僚がテキパキと仕事をこなす姿を見て、自分だけが取り残されているような焦りや不安を感じてしまうことはありませんか?私も社会人になりたての頃は、そんな気持ちで毎日胸がいっぱいでした。上司への報告が怖かったり、山積みの仕事の優先順位がわからなくなってパニックになったり。そんな経験からくるストレスは、決して小さなものではありませんでした。
でもそれも社会人経験を積むと器用に立ち回れるようになりますよね。そして長く社会人生活を送っているといろいろなものが見えてきます。そんな私の経験から、仕事ができない人と仕事ができる人の違いや特徴、共通点などを私なりに分析してみました。
私の経験から思う、仕事ができないと感じる人の共通点
まずは、今の自分の状況を客観的に見てみましょう。私がこれまで多くの職場で見てきた、仕事ができていない人に共通する特徴を挙げてみました。
特徴1:時間の使い方が苦手で、いつも締め切りに追われている
「気づけばもう夕方…」「あの仕事、まだ手をつけていなかった!」なんてことはありませんか?時間の見積もりが甘く、一つの作業に思った以上に時間をかけてしまう人。その結果、常に締め切りに追われ、精神的な余裕がなくなってしまいます。
そのような人に共通することとして、常にデスクトップ上にファイルが散乱していたり、机の上が整理されていなかったりするのも、頭の中が整理できていないサインだと思います。
特徴2:何でも後回しにする人、取り組むまでが遅い人
こういう方は単純にビジネスチャンスを逃します。
特徴として、パソコンのタブが何十個も開いていたり、メールやチャットの返信が遅かったりする人です。頭の整理がされていないことに加えて、仕事に余白がなく、判断も遅い人が多いです。
仕事ができる人は人に関わる仕事やレスを即反応して、その後、一人でじっくりと考え行動するパターンが多いです。いつも締切ギリギリにやるのではなく、すぐやる人は大抵、仕事ができる人が多いと思います。また、本当に成果を出す人は、何をやらないかを決めるのも上手です。
特徴3:今までやってきたことに固執する人、変化を恐れる人
会社の規模を大きくするためには改革も大事です。新しいことにチャレンジしない人というのはどんどん活躍の場を失っていきます。反対にチャレンジする人は、自分がこれまでやってきたことを全て手放しででも、思い切った方向転換ができる人です。
変化を恐れる人の特徴は、今までやってきたことに疑問を持たなかったり、変えようとする人の意見を否定したり、協力しなかったりする特徴があると思います。
こういう人はどこの会社にもいると思いますが、文句や意見ばかり言う評論家のような立場で、生産性を下げていることになります。このような人にはなりたくないので私も気をつけようと思います。

なぜ仕事がうまくいかないのか?3つの根本原因
なぜ仕事うまくいかないのか、その理由を私なりに考えてみました。
原因1:仕事の全体像が見えていない「木を見て森を見ず」問題
頼まれた作業をただこなすだけで、その仕事がプロジェクト全体の中でどのような位置づけで、何のために必要なのかを理解していない状態の人ってよくいます。仕事も人生も全体像を考えることってとても重要だと思います。
原因2:完璧主義すぎて、60点のスピード提出ができない
こういう人もよくいます。資料はまだ?と上司に聞かれて、まだできていませんと言うタイプ。そして出てきた時には、大抵やり直しをさせられ、さらに期日が迫っている状態の人。
ビジネスの世界では、多くの場合、100点のアウトプットを1週間後に出すよりも、60点のものを翌日に提出する方が価値が高いことがあります。早い段階で上司や関係者に方向性の確認をすることで、大きな手戻りを防ぎ、結果的に全体の質を高めることにつながるからです。
原因3:自分一人で抱え込むコミュニケーション不足
「これは自分の仕事だから」「周りは忙しそうだから聞きづらい」といった理由で、一人ですべてを解決しようとしてしまう。このタイプはリーダーでも部下でもいますね。
仕事は多くの場合、チームで行うものです。わからないことを聞いたり、困っていることを相談したりするのは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、早めに情報共有することで、周りが持つ知識や経験という力を借りることができ、より早く、より良い成果につなげることができます。

成果を出すための思考法を学ぶ
私の経験と分析を書きましたが、では実際に成果を出すためにはどうしたら良いか。日本の著名な経営者たちの考え方から、仕事の成果を出すためのヒントを学びましょう。
孫正義氏の「No.1戦略」:まず一番重要な問題は何かを考える
ソフトバンクグループの孫正義氏は、常に「No.1」を目指すことで知られています。たくさんのタスクがある中で、この仕事の成果を最大化させるために、今一番解決すべきボトルネックは何か?を常に自問自答することが大事とのこと。最も重要な一点に集中することで、大きな成果を生み出すことができます。
稲盛和夫氏の「アメーバ経営」:自分の仕事の採算を意識する
京セラやKDDIを創業した稲盛和夫氏が提唱した「アメーバ経営」は、組織を小さな集団に分け、それぞれが独立採算で動く経営手法です。これを個人に置き換えて、「自分の時間というコストを使って、どれだけの価値(売上や貢献)を生み出しているか?」という採算意識を持ってみると、より価値の高い仕事に時間を使おうという思考にシフトされるそうです。
南場智子氏の「不格好経営」:失敗を恐れず、まず行動してみる
DeNAの創業者である南場智子氏の著書『不格好経営』では、数々の失敗談が赤裸々に語られています。完璧な計画を立ててから動くのではなく、まずやってみる。失敗したら、そこから学んで修正していく。この「まず行動する」という姿勢が、停滞を打ち破るカギになります。60点の出来でもいいので、まずは一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。
まとめ:小さな行動の積み重ねが、未来のあなたを創る
私もまずは意識から変えて仕事をしてみようと思います。仕事ができるに越したことはないですし、仕事ができない人と思われて仕事するのも辛いですよね。まずは仕事のできる人の習慣を真似してみることもできそうです。
仕事が全てではないですが、1日の大半は仕事です。どうせ働くなら気持ちがよく働きたいものですね。