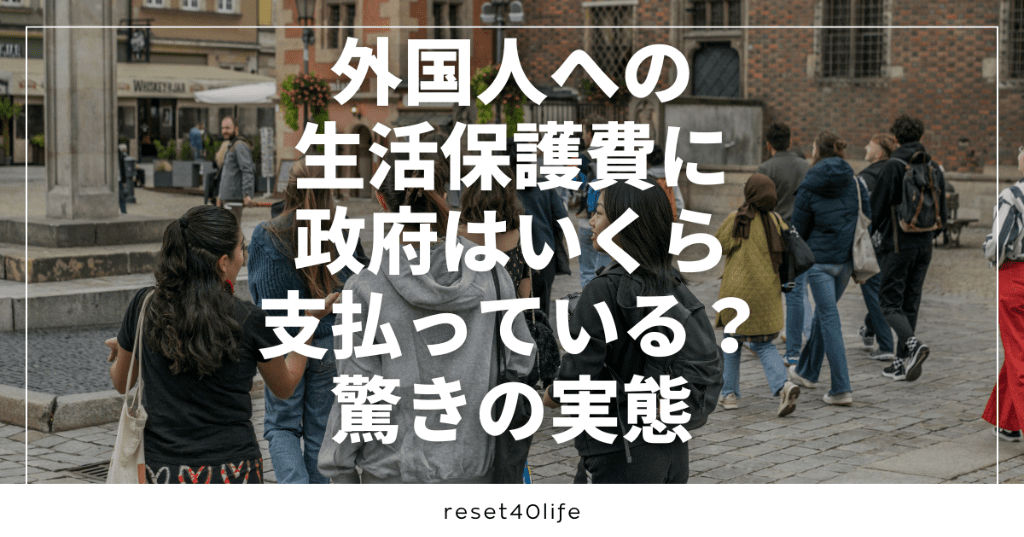先日、SNSを眺めていたら「外国人への生活保護」についての投稿が目に入りました。コメント欄は賛成、反対、さまざまな意見で溢れていて、正直、私もなんだかモヤモヤした気持ちになりました。
私が都内で暮らしていると、新宿や渋谷を歩けば、本当にたくさんの外国の方を見かけます。観光客の方もいれば、日本に住んでいる方も多いんだろうなと感じます。そして、文化や習慣の違いからくる小さなトラブルの話を聞いたり、治安について少し心配になったりするのも事実です。
そんな中で、今回の「生活保護」の問題。私たちは、毎月のお給料から税金や社会保険料を天引きという形で納めています。このお金が、病気や失業などで本当に生活に困窮してしまった日本人を支える「助け合いの仕組み」に使われる。そう理解していました。
ところが、日本に来て間もない外国の方が、税金などを納めていなくても生活保護を受給できるケースがあると聞きます。これっておかしくないですか?野田政権の時に自民党の片山さつき議員が参議院予算委員会で、外国人に支給されている生活保護費は1,200億円と発言していたそうです。
私たちが一生懸命働いて納めた税金が、本来の助け合いの輪の外で使われているような気がして、納得できません。本当に困っている日本人に充てるべきだと思います。今日は、そんな私の正直な気持ちと、この外国人への生活保護制度について調べてみたことを紹介したいと思います。

外国人への生活保護、そもそもどんな仕組み?
まず生活保護制度について調べてみました。
日本人とは違う?法律ではなく「通知」に基づく特別な措置
日本の生活保護制度の根拠となる「生活保護法」の第二条には、対象者が「国民」であると明記されています。つまり、法律上、外国人は生活保護の対象ではありません。
では、なぜ外国人に支給されているのでしょうか。
実はこれ、1954年(昭和29年)に当時の厚生省(現在の厚生労働省)が出した「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知が根拠になっています。これは法律ではなく、あくまで行政上の「当分の間の措置」として、人道的な観点から日本人に準じて保護を行う、というものなんです。
法律ではなく、一つの通知に基づいて、もう70年近くも運用が続いている。
これってどうなんでしょうか。
誰でももらえるわけじゃない?対象となる外国人の「在留資格」とは
「じゃあ、日本に来た外国人は誰でも生活保護をもらえるの?」と思うかもしれませんが、そういうわけではありません。この行政措置が適用されるのは、特定の「在留資格」を持つ外国人に限られています。
在留資格とは、外国人が日本に滞在するための許可の種類のことです。この特別な措置の対象となるのは、日本での活動に制限がなく、永住性が認められる在留資格を持つ人が中心です。ですから、観光目的の短期滞在者や、留学生などが生活に困ったからといって、すぐに生活保護を受けられるわけではないそうです。
「永住者」や「定住者」が主な対象
外国人への生活保護で、主な対象となり得るのは、以下のような在留資格を持つ人たちです。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特別永주者
これらの資格を持つ人たちは、日本社会に定着して生活していると見なされ、生活に困窮した場合には、人道的な観点から保護の対象となる、というのが現在の運用です。

受給している外国人はどれくらいいるの?世帯数と人数の推移
2022年度(令和4年度)厚生労働省「被保護者調査」のデータでは、生活保護を受けている外国人世帯は月平均で45,634世帯、人数にすると69,598人となっています。
これは、生活保護を受けている総世帯数(約164万世帯)の約2.8%を占めます。
平成29年の加藤大臣会見の中で
「個々の外国人に対してというレベルにおいては、生活保護費の額を把握しているわけではございません。ただ、生活保護の決定・実施自体が世帯単位で実施をしておりますので、保護世帯の中に日本人と外国人で構成されている混合世帯というものがあり、あるいは外国籍の中にも日本人の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、それについては把握することが困難な状況であると認識しております。」
と発言されていますが、「個々の外国人に対してというレベルにおいては、生活保護費の額を把握しているわけではございません。」まず、これが問題だと思います。
なぜ把握していないのでしょうか?普通、一般企業でも収入と支出がわかるように帳簿をつけますよね?なぜ国民の税金を使っている政府が、生活保護費にいくら使っているのか、そのうち、通知で運用している外国人生活保護費の割合がいくらかは調べる義務があると思います。
なぜ外国人に生活保護が必要と言われるの?
法律の対象ではないのに、なぜ支給が続くのでしょうか。これには、いくつかの理由や考え方があるようです。
最高裁は「国民ではない」と判断、でも自治体は支給を続ける理由
2014年、最高裁判所は「外国人は生活保護法の対象ではない」という判決を下しました。これは、法律の条文を厳密に解釈した結果です。
しかし、この判決が出た後も、国(厚生労働省)は「これまでの行政措置を変更するものではない」とし、自治体は支給を続けています。最高裁の判決は、あくまで「法律上の権利はない」ということを確認したもので、「支給してはいけない」と命じたわけではない、という解釈なんです。
これにも疑問が残ります。支給を続ける一番の理由は、人道上の配慮だとは思いますが、法律に定められていないことをダラダラと続けることにも疑問が残ります。政府は今一度、国民の声を聞いて、制度を改めるべきだと思います。
まとめ:外国人問題をもっと自分ごととして考える
外国人への生活保護の問題は、単なる問題ではありません。今は移民も増えており、私たちの税金がどう使われるのか、日本社会の秩序をどう守っていくのか、社会の助け合いの仕組みをどう維持していくのか、という私たち自身の問題の岐路に立たされていると思います。
ニュースでもナイジェリアのことが話題になっていましたが、明らかにいろいろなことがおかしくなっていると感じます。私も政治には興味がなかったのですが、最近のこの外国人問題には一種の危機を感じます。外国人を支援するなら、まず日本人を支援してほしいと強く思います。そして私たち日本国民がもっと政治に興味を持たないとと強く感じました。そしてこの外国人問題をもっと自分ごととして考えていきたいと思います。